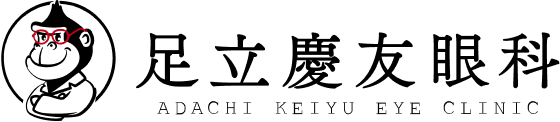網膜硝子体手術
網膜や硝子体は、物を見るために重要な働きをする組織です。これらに異常が生じると、視力の低下や視野の欠損など深刻な症状を引き起こすことがあります。網膜硝子体手術は、これら治療に用いられる手術で、視機能の回復や進行抑制に効果的です。本記事では、適応となる疾患や治療内容、手術のリスクについて詳しく解説します。
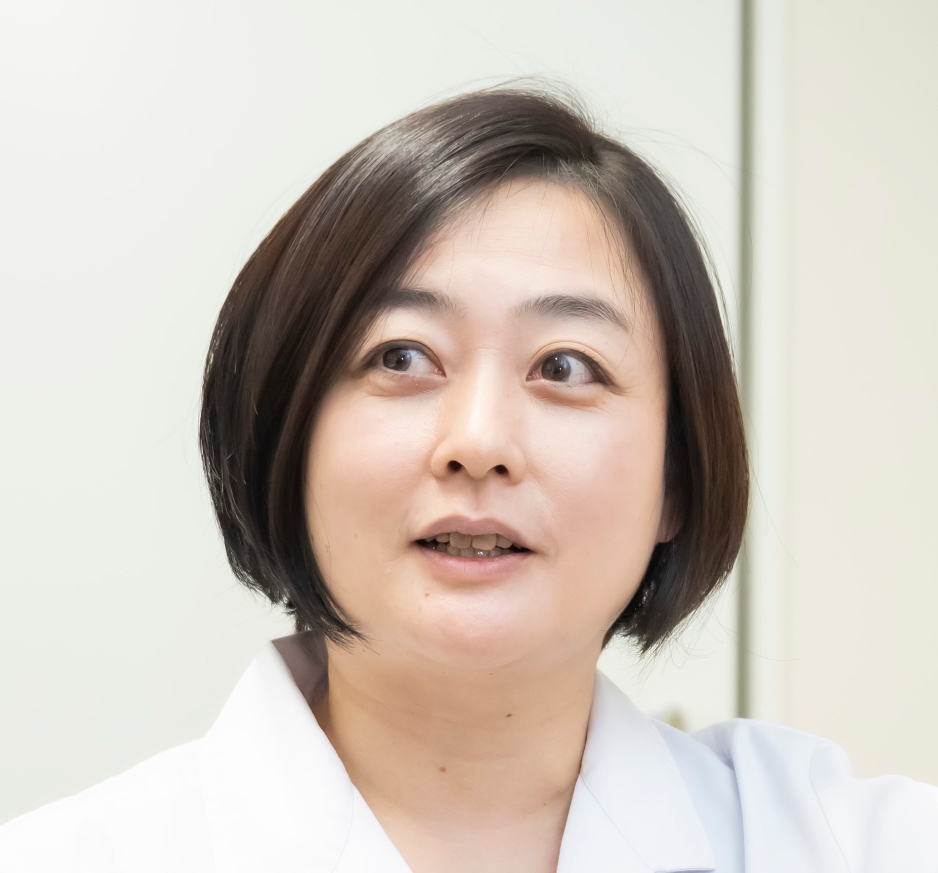
上村 文
Aya Uemura
大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
網膜硝子体手術とは

網膜硝子体疾患とは、変質・混濁した硝子体の組織を切除・除去し、網膜疾患を改善するための手術です。
眼球内は硝子体(しょうしたい)という無色透明のゼリー状の組織で満たされています。硝子体は、水晶体の後ろ側と接し、奥側は一部網膜と接しています。
99%が水分、1%がコラーゲンで構成され、「眼球の形状を保つ」「光を屈折させる」「衝撃から守る」といった重要な役割を担っています。この硝子体は、出血や炎症などにより濁ることがあり、網膜を牽引して網膜剥離を引き起こす場合もあります。
視界や視力に深刻な影響を及ぼすため、これらの疾患がある場合は、治療として「網膜硝子体手術」が行われます。近年では低侵襲で安全性の高い技術が進歩しており、多くの患者さんに有効な治療法となっています。
網膜硝子体手術はどんな手術?

網膜硝子体手術は、非常に繊細で高度な技術を要する手術で、例えるなら「ガムをティッシュペーパーからはがす」ような慎重さが求められます。
通常は局所麻酔で行われ、白目の部分に極小の穴を3か所開け、そこから器具を挿入して手術を進めます。灌流(かんりゅう)器具で眼圧を保ちつつ、照明器具や硝子体カッターを用いて濁った硝子体や膜状の組織を切除・吸引除去します。
疾患によっては、網膜にレーザーを照射したり、膜をピンセットのような器具で剥がしたりといった処置も必要となります。網膜剥離や黄斑円孔などでは、手術の終盤で灌流液をガスに置き換えます。
手術時間は疾患の重症度によって異なり、軽症例で約30分、重症例では2時間以上かかることもあります。
足立慶友眼科の網膜硝子体手術

身体への負担が少ない手法を採用!
当院では、小切開硝子体手術「MIVS(Microincision Vitreous Surgery)」と呼ばれる最新の手法を採用しています。
MIVSは、非常に細い器具を専用の機器で眼内に挿入して行う低侵襲手術で、術後の回復が早く、身体への負担も少ないのが特徴です。手術成績も良好で、安全性の高い方法として全国的に広く取り入れられています。
足立慶友眼科では、このMIVSを用いて、すべての網膜硝子体手術を日帰りで実施しています。手術時間は通常の硝子体手術で約20分、白内障手術などを同時に行う場合でも30〜40分程度で終了します。
患者さまの快適な日常生活への早期復帰を第一に考えた手術体制を整えています。
最新の硝子体手術装置を導入!
足立慶友眼科では、最新の硝子体手術装置「アルコン・コンステレーション®ビジョンシステム」を導入しています。この装置は従来機種に比べて硝子体のカットスピードが大幅に向上しており、より短時間で効率的な手術が可能となりました。
同時に、灌流圧(眼内圧)を精密にコントロールできる灌流圧供給システムも備えており、術中の眼球状態を安定させることで、安全性がさらに高まりました。
網膜硝子体手術の適応となる疾患

網膜硝子体手術は、硝子体や網膜に異常が生じた際に行う手術で、さまざまな疾患が適応となります。
適応となる主な疾患は下記になります。
- 網膜剥離
- 黄斑円孔
- 黄斑上膜(前膜)
- 網膜静脈閉塞症
- 糖尿病網膜症
これらの疾患は、視野のゆがみ・欠損・急激な視力低下等を引き起こし、進行すると視力回復が困難になる可能性もあるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
当院では、これらの疾患に対し、安全で精密な日帰り手術を提供しています。
網膜剥離
網膜剥離とは、眼の奥にある薄い神経の膜「網膜」が眼球の内壁(眼底)から剥がれてしまう病気です。
原因は様々ですが、加齢による硝子体の変化や、近視、外傷、糖尿病などが関与することがあります。
初期には光が走るような「光視症」や「飛蚊症」が現れ、進行すると視野が欠けるなど、急激な視力低下を引き起こすこともあります。放置すると失明のリスクもあるため、早期発見・早期手術が非常に重要です。
網膜硝子体手術で、剥がれた網膜を眼底に回復させ、再剥離を防ぐ処置が行われます。
黄斑円孔
黄斑円孔は、網膜の中心にある「黄斑部」に丸い穴が開いてしまう病気です。
黄斑は視力にとって最も重要な部分であり、ここに異常が起こると物が歪んで見える(変視症)・中心が暗く抜ける・視力が急激に低下するといった症状が現れます。
主に加齢に伴う硝子体の収縮が原因で起こり、特に中高年の女性に多くみられます。自然に治癒することはほとんどなく、放置すると視力の回復が難しくなるため、早期の網膜硝子体手術が有効です。
手術では、黄斑を引っ張っている硝子体や膜を除去し、穴の自然閉鎖を促します。
黄斑上膜・黄斑前膜
黄斑上膜(または黄斑前膜)は、網膜の中心にある黄斑部に、膜のような組織が張ってしまう病気です。
この膜が収縮すると黄斑が引っ張られ、物がゆがんで見える(変視症)、文字が二重に見える、視力が低下するといった症状が現れます。加齢に伴う硝子体の変化が主な原因で、中高年に多く見られます。
症状が軽度であれば経過観察となりますが、日常生活に支障が出る場合には網膜硝子体手術が必要です。
手術では、膜をピンセットのような器具で丁寧に剥がし、黄斑部の形を整えることで、視力やゆがみの改善が期待されます。
網膜静脈閉塞症
網膜静脈閉塞症は、網膜内の静脈が詰まることで血液の流れが滞り、網膜に出血や浮腫(むくみ)を引き起こす病気です。
主な原因は高血圧や動脈硬化、糖尿病等で、特に中高年に多く発症します。視界が急にかすむ・ぼやける、視野の一部が見えにくくなるなどの症状があらわれます。網膜黄斑部に浮腫が生じると視力が著しく低下することもあります。
状態により注射治療やレーザー治療が行われますが、出血や浮腫が重度な場合は網膜硝子体手術が適応となります。手術により、濁りや膜を除去し、視機能の改善を図ります。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、糖尿病による高血糖が原因で網膜の血管が傷み、出血や血管の閉塞、むくみを引き起こす病気です。
進行すると新生血管ができやすくなり、硝子体出血や網膜剥離を招くこともあります。初期には自覚症状が少なく、定期的な眼科検査が重要です。症状が進むと視力低下や視野欠損が現れ、生活の質に大きな影響を及ぼします。
治療はレーザーや抗VEGF注射が中心ですが、硝子体内の出血や網膜剥離が起こった場合は、網膜硝子体手術が必要となります。手術で出血や病的組織を除去し、視力の維持・改善を目指します。
網膜硝子体手術のリスク

網膜硝子体手術は広く安全に行われている手術ですが、まれに合併症が起こることがあります。合併症は手術技術や術後管理の進歩により大幅に減少していますが、患者さまの全身状態や眼の状態によってはリスクが高まることもあります。
術前に十分な説明を行い、術後は適切なケアと定期検査を徹底することで、安全に手術を受けていただけるよう努めています。
網膜硝子体手術の合併症
術後眼内炎
創口から細菌感染を起こして発症します。現在の手術方法では、創口が小さく、決められた注意事項を遵守すれば、この合併症を起こすことはまずありません。
しかし、万が一感染がこじれると大きな後遺症を残すことがあり、速やかな診断と治療が不可欠です。
駆逐性出血
駆逐性出血とは、手術中に急激な血圧上昇や強い緊張、咳き込みなどの負荷が加わることで、目の奥にある動脈から大量の出血が起こる極めてまれな合併症です。
発生頻度は約10,000例に1回と非常に低いものの、起こると視力が大きく損なわれる深刻な事態となります。
網膜剥離
網膜硝子体手術後に、何らかの原因で網膜剥離が再発する場合があります。
術後の網膜剥離はまれですが、その場合には、再度硝子体手術を行い、剥がれた網膜を眼底に戻し固定する必要があります。
お問い合わせはこちら
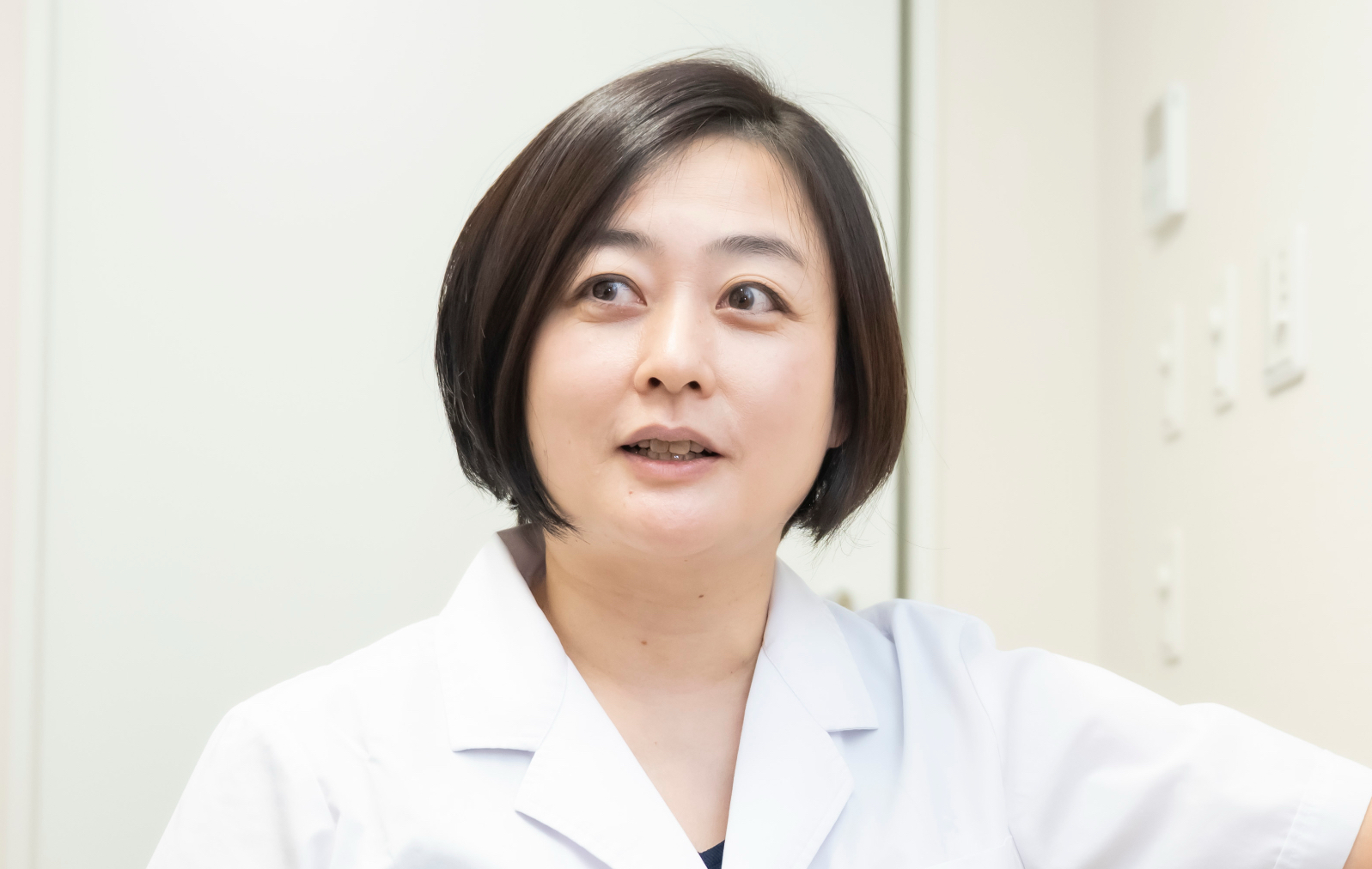 足立慶友眼科 院長
足立慶友眼科 院長
上村 文
Aya Uemura大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
医師について詳しく