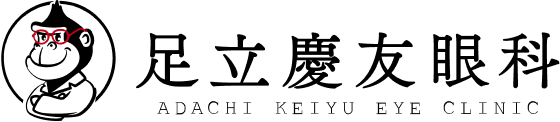糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症として日本における成人の失明原因の上位に位置する重要な病気です。血糖値が高い状態が続くことで、網膜の細い血管が損傷し、視力低下を引き起こします。初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことが多いです。この記事では、糖尿病網膜症の原因や症状、治療法について解説しています。
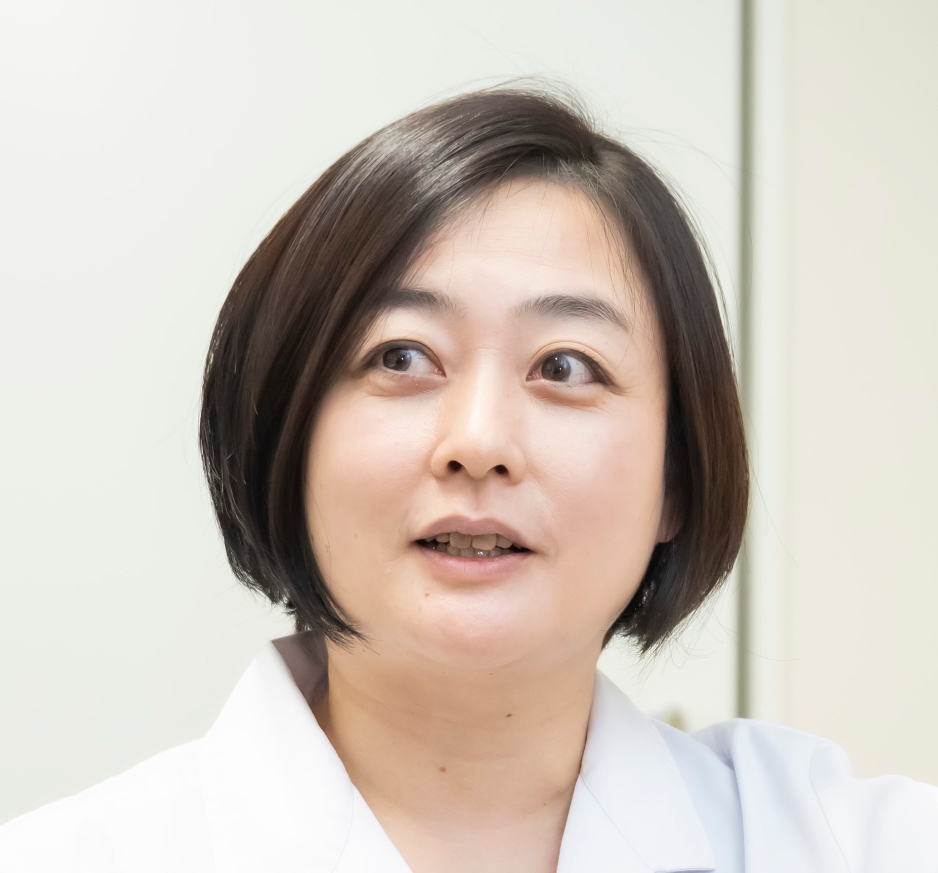
上村 文
Aya Uemura
大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
糖尿病網膜症とは

糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症のひとつであり、日本では成人の失明原因の上位に挙げられます。糖尿病により血糖が高い状態が長期間続くと、網膜の細い血管が少しずつ損傷され、変形や閉塞を起こしてしまい、視力が低下します。
この病気の厄介な点は、少しずつ進行するにもかかわらず、かなり進行するまで自覚症状がないことが多い点です。そのため、自覚症状がないまま放置してしまい、「急に見えなくなった」「目の前が真っ暗になった」といった深刻な視力障害に突然襲われることがあります。
POINT
生涯にわたって良好な視力を維持するためにも、糖尿病と診断されたら、必ず眼科を受診しましょう。
糖尿病網膜症の分類

糖尿病網膜症は、糖尿病の発症から約5年を目安に発症するとされ、10〜15年で約50%以上の患者さんに糖尿病網膜症が認められるといわれています。
この病気は進行の程度によって、初期の「単純糖尿病網膜症」、中期の「増殖前糖尿病網膜症」、末期の「増殖糖尿病網膜症」と大きく三つの段階に分類されます。
それぞれのステージで症状や治療方針が異なるため、進行段階に応じた適切な管理と治療が必要です。
単純糖尿病網膜症(初期)
糖尿病網膜症の初期段階である「単純糖尿病網膜症」では、毛細血管瘤(細い血管の壁が盛り上がってできる小さなこぶ)や、点状・斑状出血といった小さな出血が網膜にあらわれます。
また、血管から漏れ出たたんぱく質や脂肪が網膜に沈着し、「硬性白斑」と呼ばれるシミを形成することもあります。
この時期の治療としては、内科での血糖コントロールに加え、網膜の血流を改善する内服薬の服用等が行われます。糖尿病網膜症の進行を抑えるためには、眼科と内科の連携が欠かせません。
症状
この段階では、自覚症状がほとんどありませんが、網膜の中でも視力に重要な「黄斑部」にむくみ(黄斑浮腫)が生じた場合には、視力の低下を自覚することがあります。
初期の単純糖尿病網膜症では症状はほとんどありませんが、
定期的に眼科検査を受け、血糖値のコントロールを行うことで、悪化させないことが重要です。
増殖前糖尿病網膜症(中期)
単純糖尿病網膜症がさらに悪化した段階で、網膜の細い血管が広範囲にわたり閉塞してしまいます。その結果、網膜に十分な酸素が届かなくなり、体は不足した酸素を補おうとして、新しい血管(新生血管)を作る準備を始めます。
この段階では、視界がかすむといった症状を自覚することがありますが、依然として自覚症状がない場合も多く見られます。必要に応じてレーザー光凝固を行い、新生血管の発生を抑えます。
また、黄斑のむくみがある場合には、抗VEGF薬注射やステロイド薬注射等を使用した薬物療法を行います。
症状
糖尿病網膜症の怖いところは、中期である増殖前糖尿病網膜症の段階でも自覚症状がないケースが多いことです。
ただし、網膜の中心である黄斑部にむくみ(黄斑浮腫)が生じると、視力の低下を自覚することがあります。
自覚症状のあるなしに関わらず、糖尿病と診断されたら、
定期的な眼科検診や健康管理が非常に重要となることを忘れずに毎日の生活に気を配りましょう。
増殖糖尿病網膜症(末期)
糖尿病網膜症がさらに進行すると、増殖糖尿病網膜症という末期の状態に至ります。
この段階では、網膜の酸素不足が深刻になり、体は新生血管を次々と作り出そうとします。しかし、これらの新生血管は非常にもろく破れやすいため、硝子体出血を引き起こす原因となります。
硝子体は眼球の大部分を占める透明なゼリー状の組織で、この部分に出血が起こると、飛蚊症(視界に黒い影が見える)を自覚することもあります。出血量が多いと急激な視力低下につながるケースもあります。
また、硝子体出血や網膜剝離を起こすと、汎網膜光凝固術や硝子体手術が必要となる場合があります。
症状
末期には、硝子体出血により急激な視力低下が起こることがあります。
出血の量によっては、視界が突然暗くなる、黒い影が動いて見えるなどの症状を自覚するようになります。
さらに、網膜剝離が起こると、視野の一部が見えなくなる視野障害や、視力低下があらわれます。この段階では、網膜の構造そのものが大きく乱れていることも多く、それにより継続的な視力低下が生じるケースもあります。
何よりも最優先なのは、糖尿病を悪化させないことです。
内科での血糖コントロールと、定期的な眼科検診が重要になります。
糖尿病網膜症の検査

糖尿病網膜症の主な検査について説明します。
眼底検査
まず最初に行われるのが眼底検査です。目に光をあてて眼球内部を観察する検査で、必要に応じて散瞳薬(瞳孔を拡げる目薬)を使用します。
痛みはなく、目薬が少ししみる程度です。検査後はまぶしさや手元の見えづらさが5〜6時間ほど続くため、車の運転は控える必要があります。
蛍光眼底撮影
腕の血管から蛍光色素を注射し、網膜の血流や病変の状態を撮影する検査です。
通常の眼底検査では見つけにくい、血管の異常や炎症の有無、出血の原因等を調べるのに有効です。詳細な情報を得られるため、治療方針の決定に非常に重要な検査です。
糖尿病網膜症の治療

糖尿病網膜症の治療には、症状や進行の段階に応じて、次のような方法があります。
血糖コントロール
主に初期段階に用いられる治療法です。
糖尿病網膜症の治療には、内科と連携した血糖コントロールが欠かせません。まずは、基本となるのが「食生活の改善(食事療法)」と「運動療法」です。
これらを継続しても血糖値が安定しない場合には、飲み薬やインスリン注射などの薬物療法を行います。
当院は内科と併設しているため、患者様の全身状態や血糖管理について情報共有をスムーズに行い、総合的な治療を提供できる環境が整っています。
網膜光凝固術
主に中期段階に用いられる治療法です。
網膜光凝固術とは、レーザーを酸素不足の状態にある網膜に照射し、病変を焼き固める治療法です。これにより、新生血管の発生を予防したり、既に発生してしまった新生血管を減らすことで、網膜症の進行を抑制します。
注意したいのは、この治療は視力の回復を目的としたものではなく、病状の悪化を防ぐための治療です。
レーザーの照射範囲や治療回数は、進行度や部位により異なります。治療は数回に分けて行われることもあり、基本的に外来で対応可能です。
網膜光凝固術は、早い時期であれば有効性が高く、将来の失明を予防するために大切な治療です。
硝子体注射(抗VEGF治療)
主に末期段階に用いられる治療法です。
糖尿病網膜症では、VEGF(血管内皮増殖因子)という物質が増えることで、網膜の血管から液体が漏れ出し、黄斑浮腫を引き起こします。この黄斑浮腫が視力低下の主な原因となります。
抗VEGF薬は、VEGFの働きを抑え、血管の異常な増殖や液体の漏出を防ぐ薬で、眼内に直接注射して治療を行います。これにより、黄斑浮腫が改善され、視力の維持や回復が期待できます。
硝子体手術
主に末期段階に用いられる治療法です。
糖尿病網膜症の進行により、重度の硝子体出血や再発性の出血、牽引性網膜剝離が生じた場合には、硝子体手術が必要となります。この手術は非常に高度で難易度が高く、基幹病院でも専門的な技術を持つ医師によって行われています。
お問い合わせはこちら
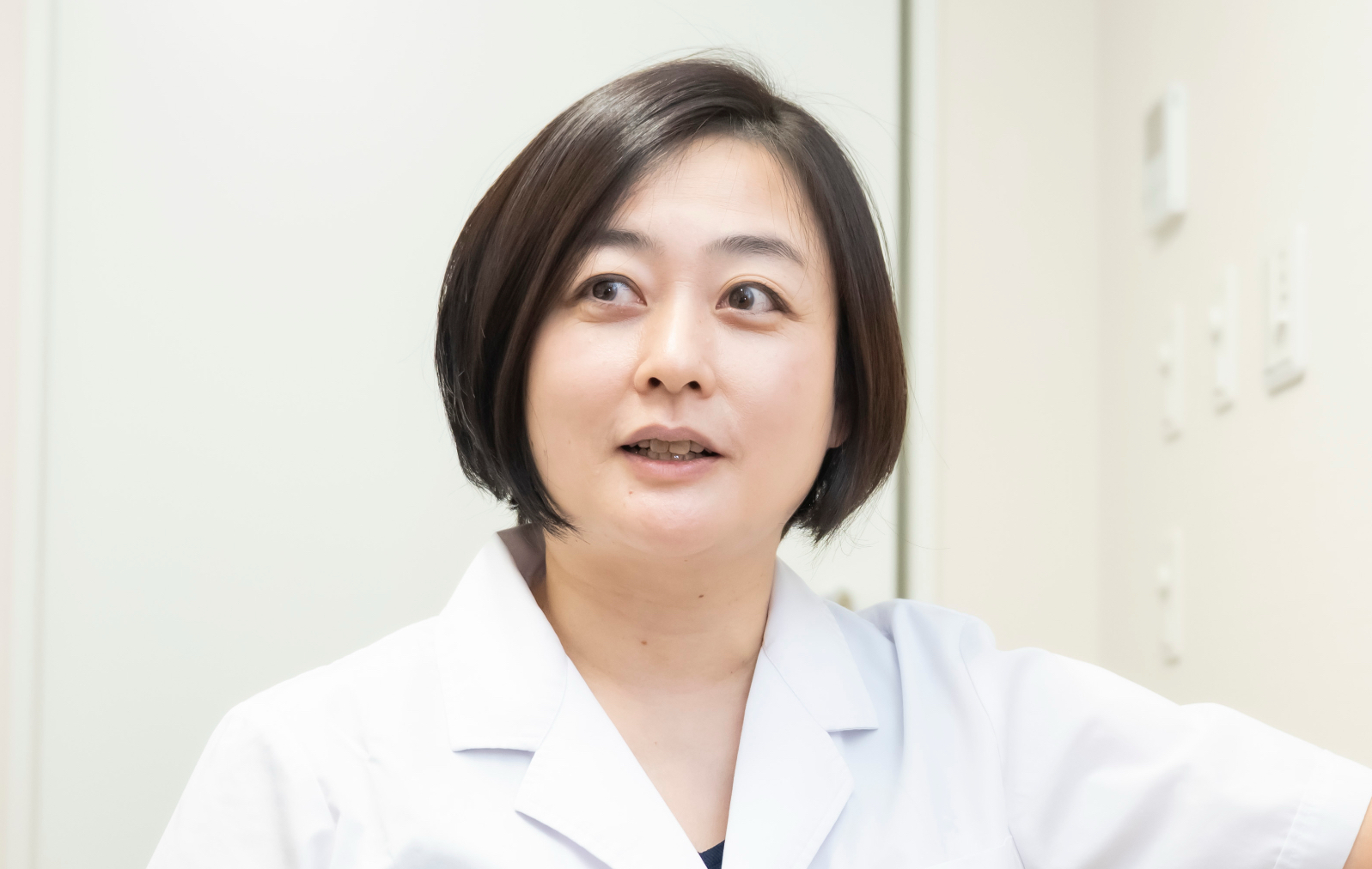 足立慶友眼科 院長
足立慶友眼科 院長
上村 文
Aya Uemura大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
医師について詳しく