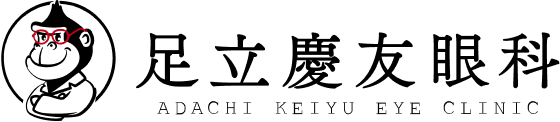飛蚊症
視界に糸くずや虫のようなものが見える、それは「飛蚊症」と呼ばれる症状かもしれません。加齢や強度近視によって生じることが多く、多くの場合は心配のないものですが、まれに網膜剥離や硝子体出血など、重大な病気のサインであることもあります。
この記事では、飛蚊症の原因、そこに潜む病気、またその治療法について詳しく解説しています。
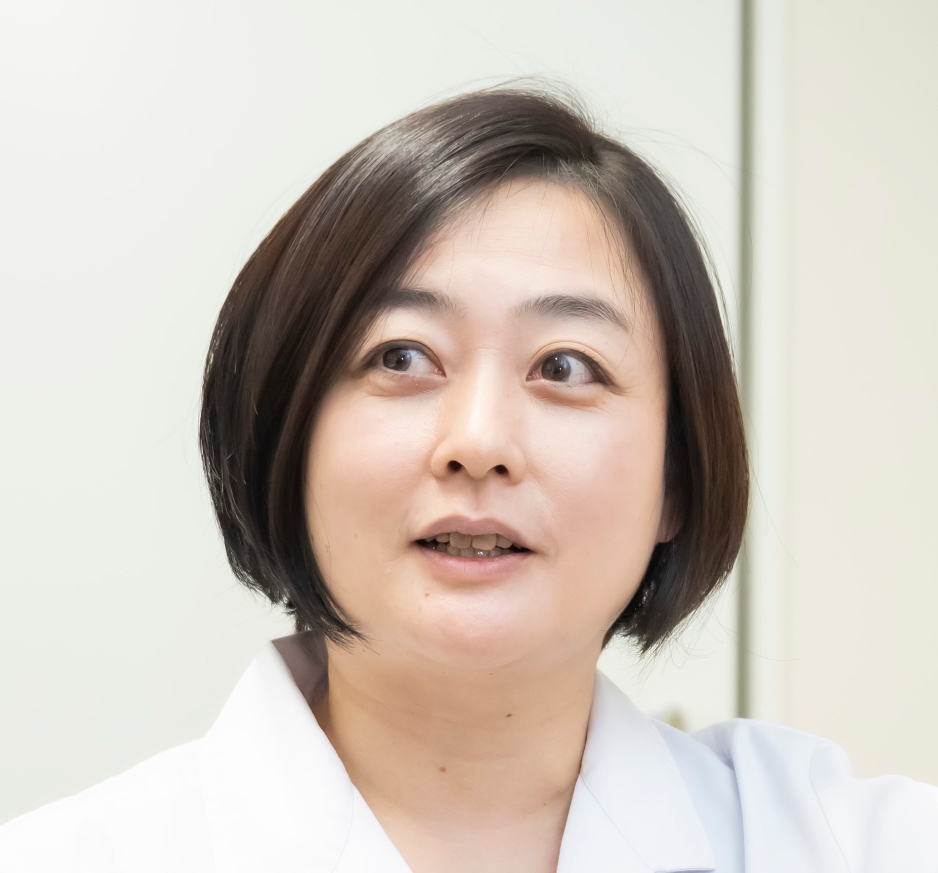
上村 文
Aya Uemura
大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
飛蚊症とは

飛蚊症とは、モノを見ているときに小さな糸くずや虫のような浮遊物が動いて見える状態のことです。
浮遊物の大きさや形状、数はさまざまであり、浮遊物は目線の動きに合わせてついてきます。まばたきをしたり、こすっても消えず、最初は鬱陶しさを感じ、気になりますが、徐々にその見え方に慣れてくる場合が多いようです。
様々な年齢層の方に起こりえますが、中でもご高齢の方や近視が強い方は症状を自覚しやすい傾向にあります。
飛蚊症そのものは必ずしも病気ではありませんが、目の疾患が原因となっている場合もありますので、浮遊物の数が増えたり、光が見えるような症状がある場合には、早めに眼科を受診しましょう。
飛蚊症は硝子体の濁りによって起こる
飛蚊症の正体は硝子体内の濁りです。
本来透明なはずの硝子体に、なんらかの原因で濁りができると、その影が網膜にうつり、目の前に見えるようになります。これが飛蚊症です。
硝子体は眼球の中を満たしているゼリー状の透明な組織で、光の通り道となる重要な部分です。そこに濁りが生じると、視界の中に糸くずや虫のような影が浮かぶように見えるのです。濁りの形や大きさ、動きは人によって異なり、眼を動かすたびに糸くずや虫の形の影も一緒に動きます。
飛蚊症の原因

飛蚊症には、加齢などによる生理的(病気ではない)な原因によるものと、網膜剥離や網膜裂孔などの病的な原因のものの2種類があります。
多くの場合は生理的な原因によるもので、心配のいらないケースがほとんどですが、中には重大な目の病気が隠れていることもあります。
生理的な原因
生理的な要素が原因となる飛蚊症は「加齢による飛蚊症」と「先天的な飛蚊症」の2種類があります。
これらは病気ではなく、体の自然な変化や生まれつきの構造により起こるものです。いずれも視力に大きな影響を与えることは少なく、時間とともに慣れて気にならなくなることが多いのが特徴です。
加齢による飛蚊症
飛蚊症の大半の原因は加齢です。年齢を重ねると硝子体が萎縮するため、濁りが生じやすくなります。
若くても強度の近視をもっていると、硝子体の変化が早く進み、飛蚊症になることがあります。こうした生理的な変化による飛蚊症は、視力に大きな障害を与えることは少ないため、経過観察となるケースがほとんどです。
先天的な飛蚊症
母体にいる胎児の頃、眼球が作られる過程では硝子体に血管があります。通常、眼球が完成すると無くなるのですが、血管のなごりが残存する人もおり、これによって飛蚊症の症状が起こります。これが先天的な飛蚊症です。
視力に大きな影響を与えることは少なく、特別な治療を必要としないことが一般的です。
病的な原因
飛蚊症の9割以上が生理的な原因によるものですが、時として重大な目の病気のサインとして飛蚊症が現れる場合があります。特に急に数が増えた場合や、視野の欠損を伴う場合は注意が必要です。
下記が飛蚊症を起こす代表的な目の病気です。
【飛蚊症を起こす目の病気】
- 網膜裂孔・網膜剥離
- 硝子体出血
- ぶどう膜炎
いずれも放置すると視力を大きく損なう恐れがあります。こうした病的な飛蚊症は、早期発見・早期治療が視力を守るカギとなりますので、違和感を覚えた際はすぐに眼科を受診してください。
網膜裂孔・網膜剥離
網膜に穴があいてしまう「網膜裂孔(もうまくれっこう)」や、網膜がはがれてしまう「網膜剥離(もうまくはくり)」は、進行すると視力低下や視野欠損が発生し、放置しておくと失明の可能性もあります。
また、強度の近視の方は、眼球の長さが通常より長いため、網膜が薄く変性しやすくなります。そこから網膜裂孔が生じる場合があるため、近視の方で飛蚊症を自覚した場合は、早めの眼底検査をおすすめします。
硝子体出血
硝子体自体は血管のない透明な組織です。高血圧や糖尿病、外傷などが原因で眼底で出血が起こると、その血液が硝子体内に溜まってしまうことがあります。これを「硝子体出血(しょうしたいしゅっけつ)」といいます。
多くの場合、出血は時間とともに自然に吸収されていきますが、うまく吸収されないと血液が光を遮り、光が網膜まで届きにくくなります。その結果、視界に黒い影や糸くずのようなものが見える飛蚊症(ひぶんしょう)を感じることがあります。
ぶどう膜炎
ぶどう膜とは、虹彩、毛様体、脈絡膜から成り、血管がたくさん通る重要な組織です。このぶどう膜やその周辺に炎症を起こした状態を「ぶどう膜炎」といいます。
ぶどう膜炎も網膜剥離などと同様に、失明に至ることが多い病気です。ぶどう膜に細菌やウイルスが侵入し、炎症が起こると、硝子体内にも混濁を生じ、飛蚊症が現れます。炎症が進行すると浮遊物が増え、視力低下につながることもあります。
再発しやすい病気のため、継続的な治療と定期的な管理が必要です。
・ 虹彩(こうさい):瞳孔の大きさを調整する
・毛様体(もうようたい):水晶体の厚みを調整し、ピント調整を行う
・ 脈絡膜(みゃくらくまく):網膜に栄養を届ける
飛蚊症の治療

生理的なものが原因による生理的飛蚊症は、特に治療の必要はありません。
しかし、前述の通り確率は低いものの、飛蚊症が重大な目の病気の初期症状として現れることもあります。
網膜裂孔の場合には、「網膜光凝固術」というレーザー治療を行います。特定の波長のレーザーを網膜に照射し、網膜を凝固させることで病気の進行を抑えます。
あくまで治療は進行を食い止めるためのものであり、元の状態に戻すことはできませんが、網膜剥離などの重篤な病気への進行を防ぐ効果があります。
網膜裂孔が進行し、網膜剥離に繋がった場合には「網膜硝子体手術」といった手術が必要となります。
いずれにせよ飛蚊症の症状を自覚した場合には、飛蚊症の原因を特定する必要があるため、できるだけ早く眼科を受診するようにしてください。
お問い合わせはこちら
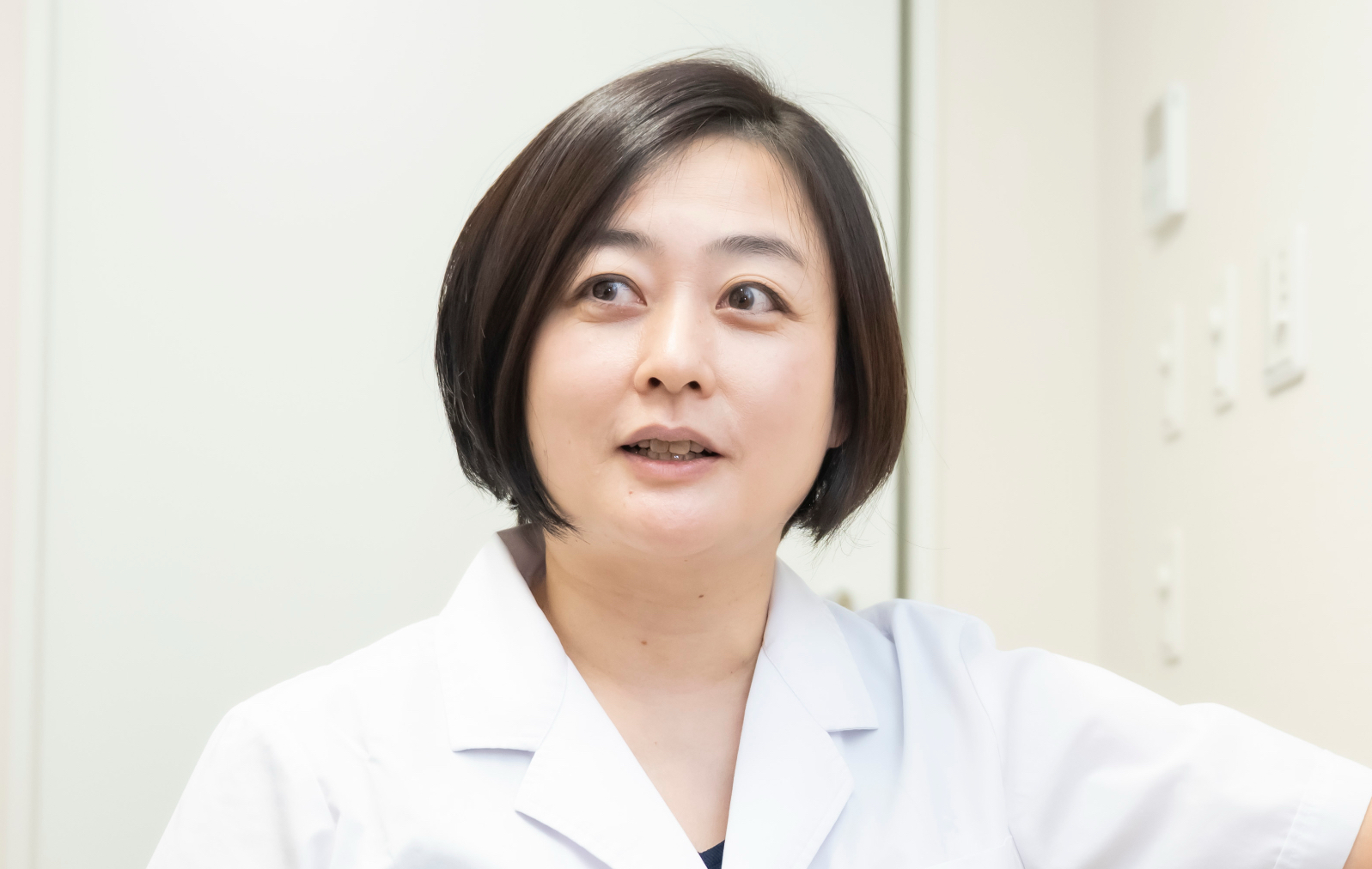 足立慶友眼科 院長
足立慶友眼科 院長
上村 文
Aya Uemura大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
医師について詳しく