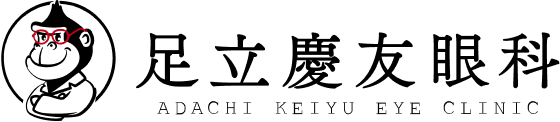加齢黄斑変性
加齢黄斑変性は、加齢によって網膜の中心部である「黄斑」が障害される病気です。ものが歪んで見えたり、視界の中心が暗くなる等の症状が現れ、進行すると視力回復が難しくなります。高齢者に多くみられる病気で、早期発見・治療が視力を守る鍵となります。この記事では、加齢黄斑変性の原因や症状、治療法、予防法まで詳しく解説しています。
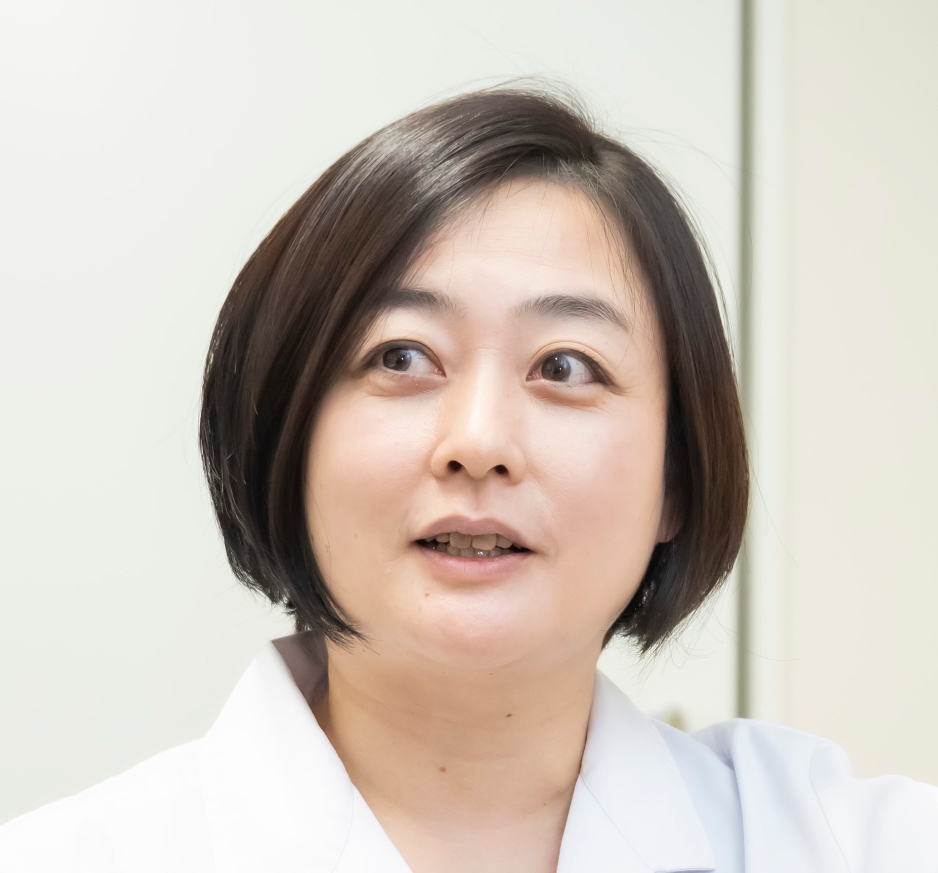
上村 文
Aya Uemura
大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
加齢黄斑変性とは

加齢黄斑変性とは、人がものを見る際に重要な役割を果たす「黄斑部」が、加齢に伴って出血したり傷んだりすることで、視力の低下を引き起こす病気です。
進行すると視力の回復が困難になることもあり、注意が必要です。欧米では成人の失明原因の第1位となっています。
日本でも高齢化や生活の欧米化の影響で患者数が増加傾向にあり、現在では失明原因の第4位を占めるようになったので注意が必要です。特に50歳以上の約1%にみられ、高齢になるほど出現頻度が高くなっています。
以前は有効な治療法がなく不治の病とされていましたが、近年では新たな治療法が開発され、多くの患者様で視力の維持や改善が期待できるようになってきました。
眼のしくみと黄斑について
眼はカメラにたとえられることが多く、内側には「網膜」というフィルムの役割を果たす膜があります。この網膜には、「視細胞」と呼ばれる光を感知する細胞がぎっしり並んでいます。
網膜の中心部にある「黄斑部」は、特別な構造を持ち、色の識別や細かいものを見る働きを担う非常に重要な場所です。
視力1.0を保つためには、この黄斑部が健康であることが必須です。黄斑部が障害されると、周辺の視野は見えていても、中心部の細かい識別が困難になります。
網膜の外側には「脈絡膜」という血管に富んだ膜がありますが、黄斑部の後ろの脈絡膜に新生血管と呼ばれる異常な血管が発生することで、黄斑部が障害され、加齢黄斑変性を引き起こします。
加齢黄斑変性の原因

加齢黄斑変性は、加齢によって黄斑部の老廃物処理機能が衰え、老廃物が網膜に沈着することが原因で起こるとされています。
加齢以外にも、紫外線の長年の曝露、喫煙、遺伝的な要因、そして食生活や生活習慣なども発症リスクを高める要因とされています。これらの要因が組み合わさることで、網膜の変性が進み、発症に至ると考えられています。
加齢黄斑変性には種類がある?
加齢黄斑変性は主に2つのタイプに分類されます。日本人に多いのは「滲出型(しんしゅつがた)」で、急速に進行しやすいタイプです。
一方で「萎縮型(いしゅくがた)」は欧米人に多く、日本人では比較的少ないタイプです。いずれも視力に影響を与えるため、正確な診断と経過観察が必要です。
滲出型とは
滲出型加齢黄斑変性は、ある日突然見え方に異変を感じることが多い進行の早い病気です。
黄斑のすぐ下に新生血管と呼ばれる異常な血管が発生し、この血管が破れて出血したり、血液の成分が漏れ出して網膜の下にたまることで、網膜の働きが妨げられ、視力が低下します。
治療が遅れると、視機能の維持が困難になり、失明につながる可能性があるため、異常を感じた際はできるだけ早く眼科を受診してください。
萎縮型とは
萎縮型加齢黄斑変性は、黄斑部にある視細胞が徐々にダメージを受け、ゆっくりと機能を失っていく病気です。
このタイプでは新生血管は出現せず、黄斑そのものが加齢に伴って萎縮していきます。そのため、突然の視力低下は起こりにくいですが、中心の「中心窩」に病変が及ぶと、はっきりとした視力障害が現れます。
また、萎縮型が進行すると、滲出型に移行することもあるため、定期的な眼科検診と経過観察が重要です。
加齢黄斑変性の症状

加齢黄斑変性になると以下のような症状が現れます。
- ものが歪んで見える
- 視界の中心が暗くなる
- 中心が見えづらい
- 視力が低下する
- ぼやける、不鮮明になる
- テレビが白黒に見える
- 人の顔がゆがむ
- 画面が波打って見える
加齢黄斑変性の初期症状は、視界の中心が見づらくなることが特徴です。初期の段階から完全に見えなくなることはありませんが、黄斑部に水がたまり腫れることで、視界がゆがんだり、ぼやけたりすることがあります。
最初は片目だけに症状が出ることも多く、気づかないうちに進行していたという方もおられます。また、加齢による変化だと思い放置されがちですが、放置するほど治療が難しくなるため、早期発見・治療が極めて重要です。
加齢黄斑変性の検査

加齢黄斑変性の診断には以下の検査が行われます。
1.視力検査
他の眼疾患と同様、視力低下の有無を確認します。
2.眼底検査
瞳孔を広げる目薬を使用し、網膜や黄斑部の状態を詳しく観察します。
3.蛍光眼底撮影
腕に蛍光色素を静脈注射し、眼底の血管の状態を撮影します。新生血管の有無や形、位置、活動性を調べます。
4.光干渉断層計(OCTスキャン)
数秒で黄斑部の断層画像が得られる非侵襲的な検査です。診断だけでなく、治療効果の評価にも有効です。
加齢黄斑変性の治療

加齢黄斑変性の治療法は、タイプに応じて異なります。滲出型と萎縮型のそれぞれの治療法を下記にて説明します。
滲出型の治療
滲出型加齢黄斑変性の治療には、硝子体注射(抗VEGF薬)、 光線力学的療法があります。
硝子体注射(抗VEGF薬)
原因となる新生血管の成長を促進するVEGF(血管内皮増殖因子)というたんぱく質を抑える治療法です。VEGFを抑える薬剤を目に直接注射することで、加齢黄斑変性の原因にアプローチします。一般的に最初の3回は毎月連続で注射を打ち、その後は定期的に検査をしながら必要に応じて注射をします。
光線力学的療法
硝子体注射が承認される以前に一般的に行われていた治療法で、光に反応する薬剤を腕の静脈から注射し、病変部を特定した上で、弱いレーザーを照射する治療法です。現在は単独で行われることはほとんどなく、硝子体注射と併用して行うことが一般的です。
萎縮型の治療
現在のところ、萎縮型加齢黄斑変性に対する有効な治療法は確立されていません。
視細胞の萎縮が進行するのを完全に止めることは困難であり、早期の治療法の開発が求められています。
現在できることは、進行を抑えるための生活習慣の見直しやサプリメントの服用、定期的な検査による経過観察が中心となります。
加齢黄斑変性の予防

日常生活での心がけ、生活習慣の見直しで加齢黄斑変性の予防が期待できます。
1.禁煙
喫煙者は非喫煙者に比べ、加齢黄斑変性の発症リスクが高まります。煙草がやめられない方は、禁煙外来に通う等をして早期の禁煙をしましょう。
2.サプリメント
ビタミンC・E、βカロチン、亜鉛等、抗酸化ビタミンや、抗酸化酵素に関わるミネラルを含むサプリメントの服用が推奨されます。特に片目に発症が認められる方は積極的に摂りましょう。
3.食事
オメガ3脂肪酸を含む赤身の魚、ルテインを含むホウレン草やケール、ブロッコリー等の野菜もおすすめです。緑黄色野菜や魚中心の食事が好ましいといえます。
4.紫外線対策
紫外線は網膜にダメージを与えるため、日常的にサングラスで眼を保護することを習慣にしてください。
お問い合わせはこちら
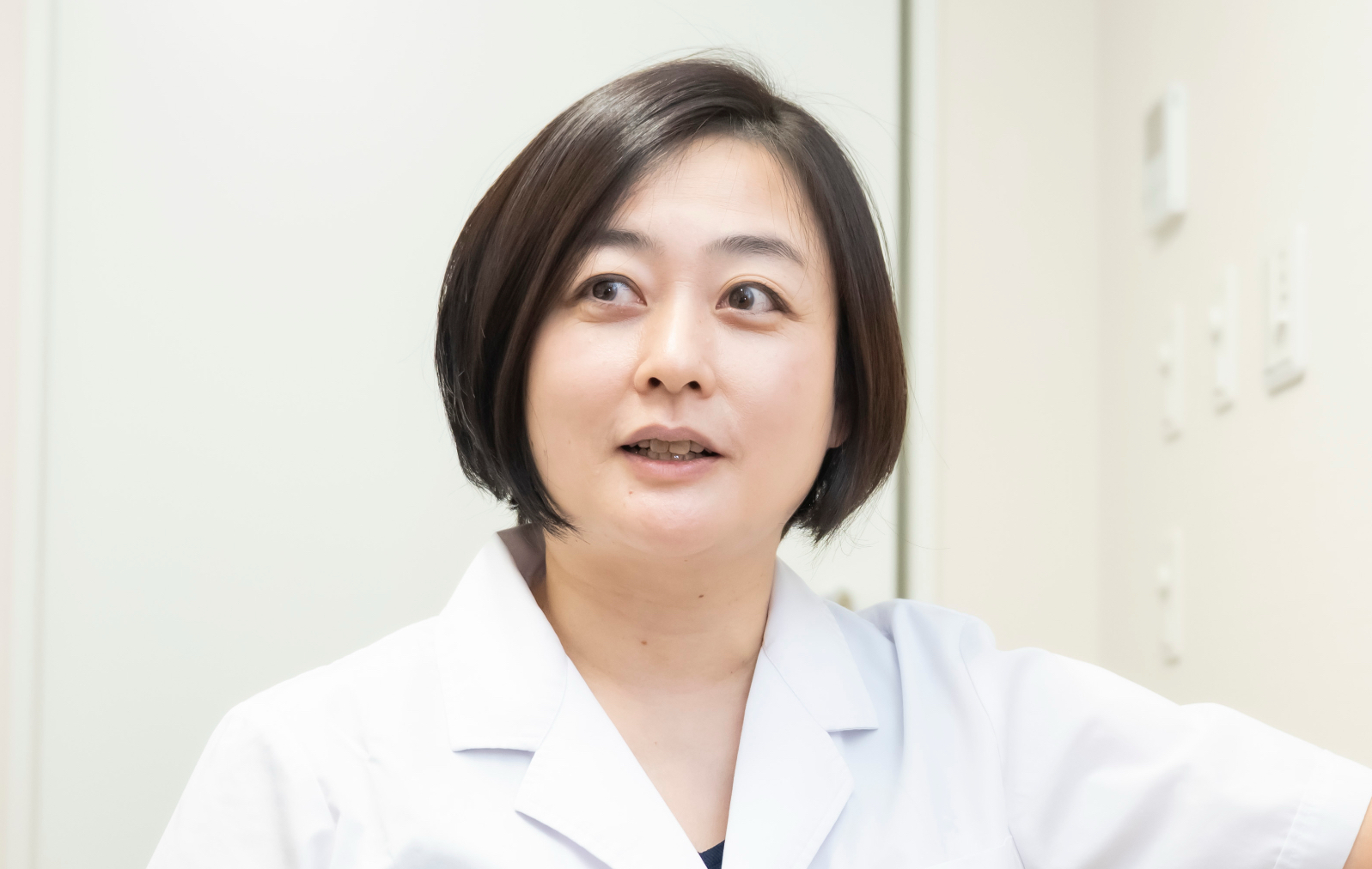 足立慶友眼科 院長
足立慶友眼科 院長
上村 文
Aya Uemura大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
医師について詳しく