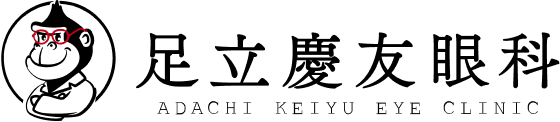屈折異常
ものが見えづらい、ぼやけて見えるといった症状の多くは、「屈折異常」と呼ばれる目の状態が原因となっていることがあります。
屈折異常には、近視・遠視・乱視といった種類があり、それぞれで見え方や対処法が異なります。この記事では、屈折異常のそれぞれの特徴や検査方法、治療法について詳しく解説しています。
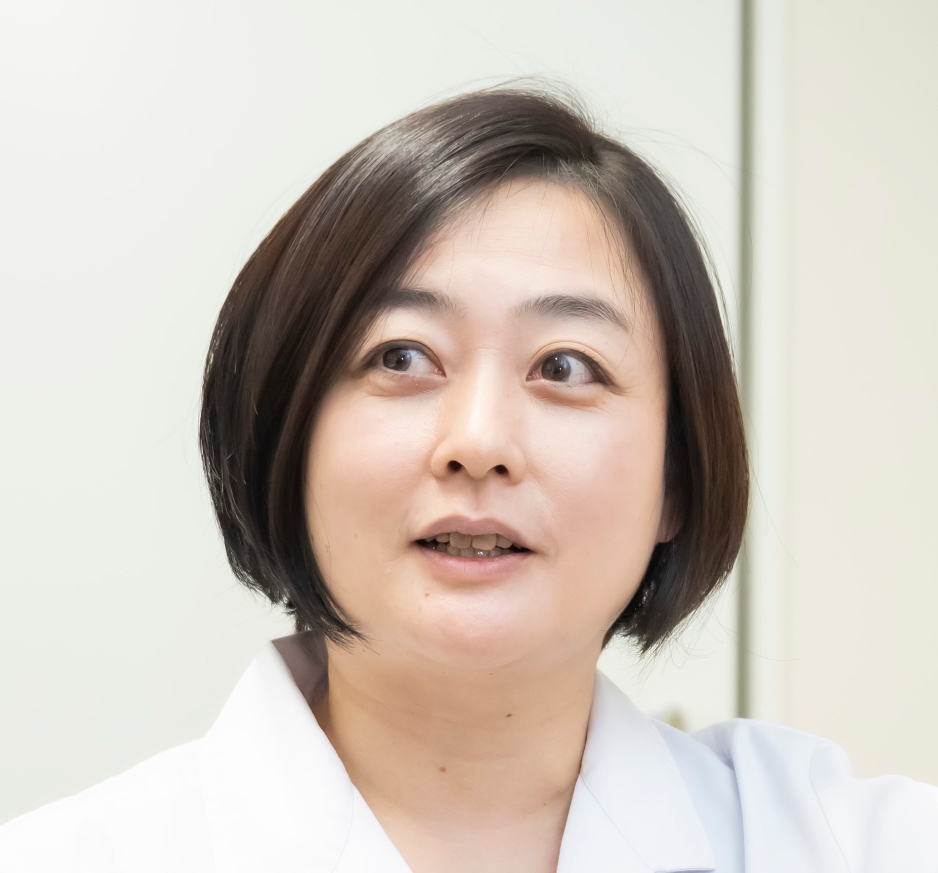
上村 文
Aya Uemura
大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。
屈折異常とは

目の構造はカメラに例えると「角膜」と「水晶体」が光を拾うレンズで、「網膜」が像を生成するフィルムにあたります。目に入った光が角膜と水晶体で屈折した後、網膜にきちんと像を結べばはっきりと見えます。この状態を「正視」といいます。
しかし、角膜や水晶体の屈折力が強すぎたり、逆に弱すぎたり、あるいは眼球が長かったり短かったりすると、光が網膜に正しく届かず、ピンボケになります。これを屈折異常と呼び、主に「近視」「遠視」「乱視」の3種類に分類されます。
近視について
近視とは、目に入った光が網膜の手前で像を結ぶ状態を指します。これは、角膜や水晶体の屈折力が強すぎたり、眼球が長いために光が正しく網膜に届かず、近くのものははっきり見えるが遠くのものがぼやけて見える状態です。
近視の原因としては、「遺伝的要因」と「環境的要因」がそれぞれ関与していると考えられています。近視が進行すると、眼球の形状が変化し、視力の低下が進むため、早期に適切な治療が必要です。
遺伝的要因
遺伝的要因とは、親から受け継いだ遺伝子が原因で近視になってしまうことです。
たとえば、両親とも近視ではない場合に比べて、どちらかの親が近視の場合、お子さんの近視リスクは約2倍。両親ともに近視の場合は約5倍にまで高まると言われています。
近視には2つのタイプがあり、メガネやコンタクトで視力を補正できる「単純近視」と、視力補正が難しく、網膜剥離などの合併症を起こしやすい「病的近視」に分けられます。特に後者の「病的近視」は遺伝的な要因が強いとされ、注意が必要です。
環境的要因
環境的要因とは、日常生活で目に良くない環境や習慣が原因となり、近視になってしまうことです。
近くのものを長時間見続ける生活が続くと、目のピント調整を担う毛様体筋が過剰に緊張し、水晶体の屈折力が強くなることで、近視になりやすいと言われています。
以前は、近くを見続ける行為として「読書のしすぎ」がよく指摘されていました。しかし最近では、スマートフォンやタブレット、パソコン、ゲーム機など、電子デバイスを日常的に長時間使用することが主な原因の一つと考えられています。
遠視について
遠視とは、目に入った光が網膜の後ろで像を結ぶ状態を指します。これは、角膜や水晶体の屈折力が弱かったり、眼球が短いために光が正しく網膜に届かず、ものがぼやけて見える状態になります。字面から遠くのものがよく見える状態と勘違いしがちですが、近くのものも遠くのものもぼやけて見えるのが遠視です。
若い人や目の調整力が十分に働いている場合は、遠視の影響が軽減されることがありますが、高齢になると調整力が弱まり、近くのものが見えづらくなることがあります。
乱視について
乱視とは、目に入った光が角膜のゆがみによって網膜のどこにも像を結ばない状態を指します。正常な目では、角膜が均等に湾曲していますが、乱視では角膜に歪みがあり、光が複数の焦点に分かれてしまいます。その結果、正しく像を結ばない状態になります。
乱視には、眼鏡で矯正できる「正乱視」と眼鏡で矯正できない「不正乱視」があります。
正乱視
正乱視とは、角膜や水晶体がひとつの方向にゆがんだ状態を指します。正常な角膜は球形に近いですが、正乱視の場合、角膜が楕円形に変形しているため、光が複数の焦点に分かれて網膜に結びつきます。その結果、視界がぼやけて見えたり、物体が歪んで見えたりします。
正乱視は比較的よく見られる屈折異常の一種で、視力に影響を与えるため、早期に適切な治療を受けることが大切です。
不正乱視
不正乱視とは、角膜の表面が不規則に歪んでいたり、水晶体に歪みが生じていたりすることで、目に入った光が網膜上で一点に焦点を結べない状態を指します。
原因には先天的なものと、後天的なものがあります。後天的な原因としては、角膜疾患、外傷、水晶体の異常といったケガや病気によるものです。
屈折異常の検査・診断

屈折異常の検査は「他覚的屈折検査」と呼ばれ、主にオートレフラクトメータという自動測定器を使用して行います。この検査では、角膜や水晶体の屈折力、角膜のカーブ(形状)、眼球の長さ(眼軸長)などを測定します。
測定では、機器の中の気球などの目印を見つめるだけでよく、数秒で完了する簡単な検査です。その後、得られたデータをもとに視力検査を実施し、裸眼視力(矯正なしの視力)と矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで補正した視力)を確認します。
屈折異常の治療法

治療の基本は、眼鏡やコンタクトレンズによる視力の矯正です。これらはそれぞれの屈折異常に応じて、光の屈折を調整するレンズを使用します。近視には凹レンズ、遠視には凸レンズ、乱視には円柱レンズなどが用いられます。また、ライフスタイルや年齢、矯正の希望レベルに応じて、より高度な治療法が選択されることもあります。
近年では、就寝中に角膜の形状を矯正する「オルソケラトロジー」や、点眼によって近視進行を抑制する「マイオピン治療」、角膜を削って屈折を調整する「レーシック」など、非手術・手術を含めた選択肢が広がっています。
近視の治療
近視の治療には、主に眼鏡やコンタクトレンズによる矯正が一般的です。近視の場合、眼鏡やコンタクトレンズには、光を正しい位置に集めるための凹レンズ(マイナスレンズ)が使用されます。これにより、遠くのものがクリアに見えるようになります。
近年では、「マイオピン治療」など、近視進行抑制効果が期待できる点眼薬が注目されています。また、「オルソケラトロジー」では、就寝中に特殊なハードコンタクトレンズを装着して角膜の形状を矯正し、日中の視力を改善する方法もあります。さらに、角膜を削ることで屈折を矯正し、視力を回復させる「レーシック」も選択肢となります。
遠視の治療
遠視の治療には、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正が基本となります。遠視の方には、光を網膜上にしっかり集めるための凸レンズ(プラスレンズ)が使用されます。これにより、近くのものもはっきりと見えるようになります。特に子どもの場合、強い遠視が視力の発達を妨げる恐れがあるため、早期の矯正が非常に重要です。
大人でも、軽度の遠視が原因で眼精疲労や肩こり、頭痛などが生じることがあります。その際には矯正を行うことで症状の改善が期待できます。日常生活に支障がある場合は、適切な処方の眼鏡やコンタクトレンズを装用してください。
眼鏡・コンタクトレンズについて乱視の治療
乱視の治療は、その原因と種類によって方法が異なります。正乱視の場合は、光が網膜上の一点に集まるように「円柱レンズ」を用いた眼鏡や、乱視用のソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズで矯正ができます。これにより視界のにじみやぼやけを改善できます。
不正乱視は、角膜の形が不規則であったり、水晶体にゆがみがあることが原因で、眼鏡では矯正ができず、ハードコンタクトレンズを使用して視力を補正する方法がとられます。ただし、水晶体由来の不正乱視では、ハードレンズでは矯正が困難で、原因疾患の治療が必要です。つまり、白内障の手術によって視力の改善を図ることが検討されます。乱視の治療には、その原因と種類を正確に診断し、それぞれに適した矯正方法を選ぶことが大切です。
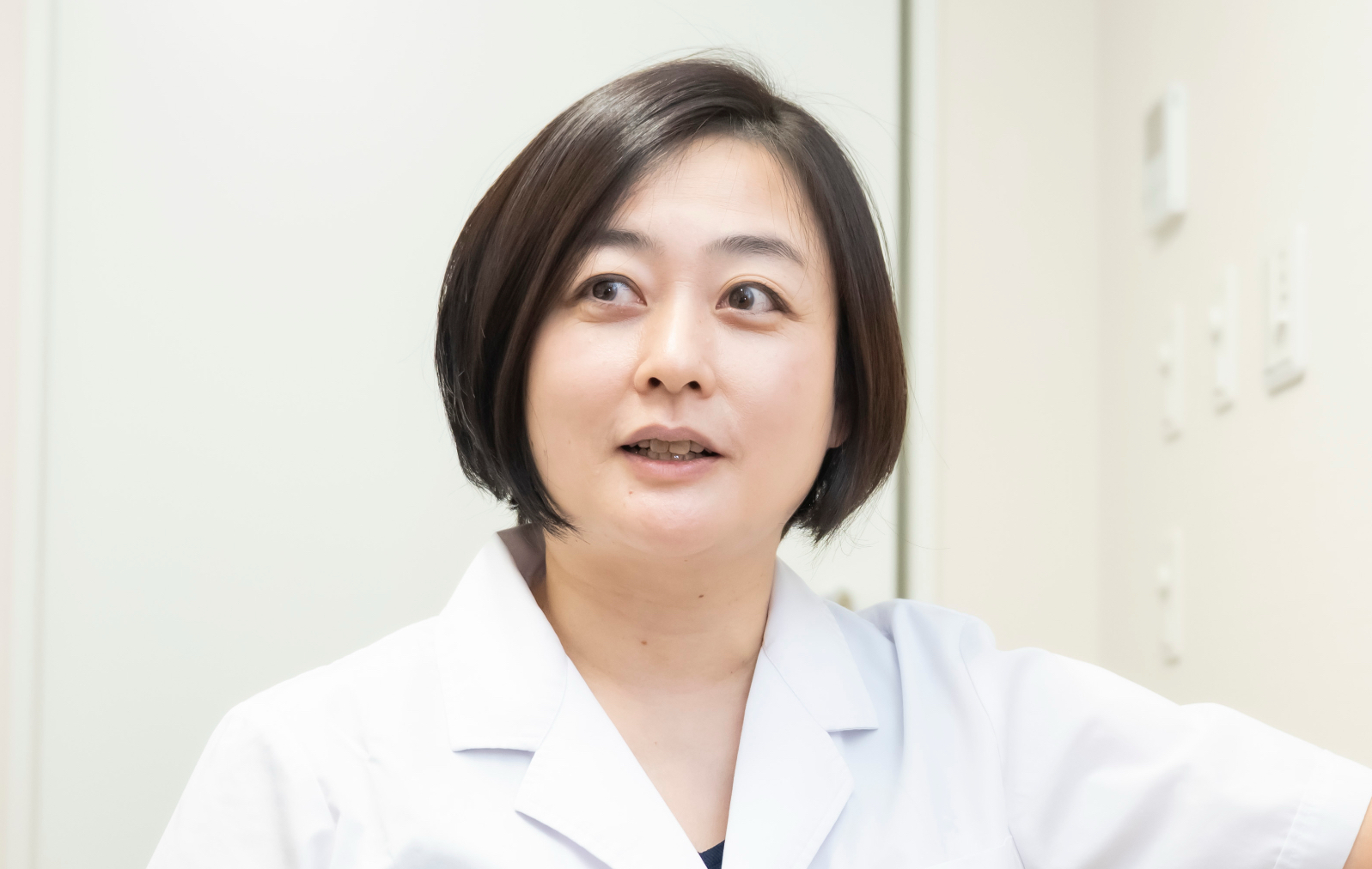 足立慶友眼科 院長
足立慶友眼科 院長
上村 文
Aya Uemura大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。
また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。